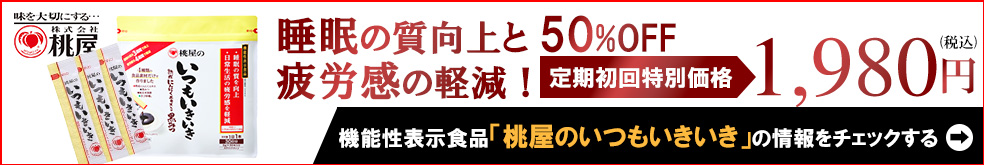すぐ眠れる7つの方法

毎日快適な睡眠をとるためには、就寝前のリラックスが重要です。
下記の7つの方法を試して、自然な眠気を促し、心地良い眠りへと導きましょう。
ゆっくりと深呼吸(腹式呼吸)をする
眠れないと思ったときは、一度落ち着いて深呼吸してみましょう。
ゆっくりとした深い呼吸は、心身をリラックスさせ、副交感神経が優位になりやすくなるといわれています。
副交感神経は、自律神経の一部でリラックス時に優位になる神経です。心拍を穏やかにし、消化を促進するなど、身体を休息状態へ導くはたらきがあります。
腹式呼吸の手順を紹介します。
1.仰向けになり、両手をお腹の上に軽く置く
2.お腹が膨らむのを感じながら5秒程かけて鼻からゆっくりと息を吸い込む
3.お腹が凹んでいくのを意識しながら口から10秒程度かけてじっくりと息を吐き出す
筋弛緩法を実践する
「筋弛緩法」は、全身の緊張をほぐしてリラックスを促す方法です。
筋弛緩法の手順を紹介します。
1.グッと手を握り、5秒程その状態を維持する
2. ゆっくりと力を抜きながら、手から力が抜けていく感覚を意識する
2.ゆっくりと脱力する。
意図的に身体に力を入れたあと一気に脱力することで、日中に蓄積された緊張をほぐし、リラックスできます。
ストレッチする
ストレッチは血行を促し、深部体温を上げてくれます。この上がった体温が下がるときに眠気が高まるため、寝る前にストレッチをすることで自然とリラックスモードに切り替わりやすくなります。
特に冬などに、「手足が冷えて寝れない……」とお悩みの方はぜひチャレンジしてみましょう。
【全身のストレッチ】
2. 反対の腕も同じように行う
2.同様に、右肘を押さえながら左側に身体を反らす
2.その状態のまま上半身をゆっくりと前に倒す
【椅子に座って行うストレッチ】
2.前に伸ばしながら背中を丸め、肩や背中の緊張をほぐす
3.身体を左右にひねって腰をストレッチする
ツボを押す
ツボ押しも手軽にできる、眠りにつきやすくなる方法です。寝る30分~1時間前に行うのがおすすめです。
特に「労宮」と「失眠」は基本となるツボです。まずはこの2つから始めて、慣れてきたらほかのツボも試してみましょう。
| ツボの名称 | 場所 | 期待できる効果 |
| 労宮(ろうきゅう) | 手を軽く握ったときの人差し指と中指の先端の中間 | 精神に働きかけ、心を静めるのに役立つ |
| 失眠(しつみん) | かかとの中央 | 睡眠に良い影響を与える |
| 百会(ひゃくえ) | 頭頂部 | 精神不安を抑え、心を落ち着かせるのに役立つ |
| 内関(ないかん) | 手首の内側 | 消化をサポートする |
| 安眠(あんみん) | 耳たぶの裏のくぼみから3cm程下 | 自律神経を休息モードに切り替えるのに役立つ |
強く押しすぎると刺激になってしまうので、適度な力加減を心がけることが大切です。
ツボを刺激する際は、息を吐きながらゆっくりと、気持ち良く感じる程度の力加減で押しましょう。
音楽を聴く
リラックスできる音楽を聴くことも、心地良い眠りを誘う方法の1つです。
リズムが一定で、音の高低差が少なく、穏やかに流れるようなメロディーの曲を選びましょう。
例えば、川のせせらぎや雨音といった自然音は、心を落ち着かせます。また、クラシック音楽やピアノの音色、オルゴールアレンジなども、心地良い眠りへと導いてくれます。
一方で、リズミカルな曲や気分が高揚するような音楽、不安感をかきたてるような曲は避けましょう。脳が刺激され、かえって寝つきが悪くなる可能性があります。
リラクゼーションミュージックやヒーリングミュージックなどが適していますが、大切なのは自分自身が心地良く感じ、ゆったりとした気分になれる音楽を選ぶことです。
軽い読書をする
就寝前の読書も、眠れないときの対処法としておすすめです。
2009年にイギリスのサセックス大学が実施した研究によると、読書を始めてから6分後に心拍数の低下と筋肉の緊張が緩和し、リラックス効果が得られたとされています。
また、読書、散歩、音楽鑑賞、ゲーム、お茶やコーヒーといったリラックス方法の中で、読書が最も高くストレス軽減効果を示したとのことです。
この研究はまだ正式な論文で示されているものではありませんが、長く眠れない時間を過ごしている場合は試してみると良いかもしれません。
寝室の温度や明るさを調整する
快適な睡眠のためには、寝室の温度や明るさの調整も重要なポイントです。
快眠のための適切な室温は20℃前後、湿度は40~70%程度とされています。
また、就寝時は不安を感じない程度に暗くしましょう。厚生労働省「健康づくりのための睡眠ガイド 2023」によると、低い照度の光であっても、睡眠の効率を下げ、途中で目が覚めやすくなることが報告されています。
カーテンは遮光機能のあるものを選び、ベッドを窓から離れた位置に配置しましょう。
就寝前のストレッチやツボ押しなどのリラックス活動を行う際も、照明は控えめにすることが大切です。部屋を薄暗くし、穏やかな気持ちで就寝準備をしましょう。
出典:厚生労働省「健康づくりのための睡眠ガイド 2023」
ベッドに入っても眠れないときの主な原因

ベッドに入ってもなかなか眠れない日が続く場合、その眠れない状態が起きている原因を把握することが、より良い睡眠への第一歩となります。
睡眠に影響が出ているときの主な原因として、下記の3つが考えられます。
・光や温度など睡眠の環境が整っていない
・夜勤があるなど生活リズムが乱れている
・ストレスを抱えている
環境面では、寝室の温度が高すぎたり低すぎたりすることや、周囲が明るすぎることで睡眠の質が低下します。
また、現代社会では、夜勤や交代制勤務などにより昼夜の区別が曖昧になりがちです。その結果、体内時計が乱れ、自然な睡眠リズムが崩れやすくなります。
さらに、仕事や人間関係の悩み事を抱えていると、心理的ストレスが要因で眠れなくなることもあります。
思い当たる原因がある場合は、まず日々の習慣を見直してみましょう。自分に合った対策を見つけることで、健康的な睡眠を取り戻すことができます。
眠れないことにお悩みの方は、下記の記事も参考になるかもしれません。
「よく眠れない…眠りが浅い人の特徴と原因、改善のポイント」
深く眠るために続けたい生活習慣

質の高い睡眠を得るためには、日々の生活習慣を整えることが大切です。
下記の4つのポイントを意識して、健康的な生活リズムを築きましょう。
ポイント1|適度な運動
良質な睡眠のために、適度な運動を取り入れましょう。
特に有酸素運動がおすすめで、中程度の運動なら掃除機がけやウォーキング、ピラティス、より強度の高い運動ではジョギングや水泳、エアロビクスなどが適しています。
週に複数回行い、習慣として定着させることが大切です。
運動は日中に行うのが理想的ですが、夕方や夜に行う場合は就寝の2時間~4時間前までに終えましょう。寝る間際に運動を行うと、脳が興奮状態になりかえって眠りの妨げになります。
ポイント2|朝食はしっかり、夜食は控える
質の良い睡眠を得るには、夜食を控え、朝食をしっかり摂ることが大切です。
特に朝食には体内時計を整える役割があるため、忙しい日もなるべく食べ物を摂るよう心がけましょう。
厚生労働省「健康づくりのための睡眠ガイド 2023」によると、1週間程度朝食を抜くと体内時計が後退し、就寝時刻が遅くなり、寝つきが悪化することが報告されています。
また、朝食を抜くことで睡眠による休養感が低下することも明らかになりました。
食事の際は、睡眠の質を上げるための栄養素も合わせて意識してみましょう。詳しくは下記の記事をご覧ください。
「睡眠の質を上げる食べ物とは?意識的に摂りたい栄養素を紹介」
出典:厚生労働省「健康づくりのための睡眠ガイド 2023」
ポイント3|規則正しい生活を心がける
夜更かしや不規則な食事時間といった生活習慣の乱れは、体内時計の乱れを引き起こし、睡眠不足につながります。
特に、労働時間が長い方は注意が必要です。睡眠の質は労働時間と密接に関係することがわかっています。
厚生労働省「健康づくりのための睡眠ガイド 2023」によると、労働時間が9時間以上の場合、睡眠時間が6時間未満になるリスクが男性で2.76倍、女性で2.71倍に増加するとされています。さらに、11時間以上になると男性で8.62倍、女性で5.59倍にまで上昇するとのことです。
勤務形態が不規則な職種でも、勤務間インターバルを活用して睡眠時間を確保しましょう。
毎日の就寝時間や食事時間を大きくずらさないようにすることが、良質な睡眠を得るためには大切です。
出典:厚生労働省「健康づくりのための睡眠ガイド 2023」
ポイント4|嗜好品は摂り方に注意する
カフェインは1日400mg(コーヒー約700ml相当)を超えると、睡眠に悪影響をおよぼす可能性があります。特に夕方以降のカフェイン摂取は、寝つきを悪くするため注意が必要です。
就寝前のアルコール摂取も控えましょう。晩酌や寝酒は、一時的に寝つきを良くする働きがあるものの、睡眠の質を低下させてしまいます。
紙巻きたばこや加熱式たばこなどに含まれるニコチンには覚醒作用があるため、喫煙も良質な睡眠を妨げる要因です。
快適な睡眠のために、嗜好品の摂取は適切に管理しましょう。
まとめ
快適な睡眠のためには、就寝前に深呼吸やストレッチ、穏やかな音楽鑑賞などでリラックスすることが大切です。
また、日中の適度な運動や規則正しい食事、嗜好品の適切な摂取など、生活習慣を整えることでより良質な睡眠を確保しましょう。