 0
0
- 桃屋壜缶詰商品のご注文は0120-003-2590120-003-259
- 桃屋いつもいきいきのご注文は0120-952-6430120-952-643
(土・日・祝日を除く)9:00 ~ 17:30
 0
0
(土・日・祝日を除く)9:00 ~ 17:30


発売当時のつゆの瓶
「つゆ」を発売したのは1976(昭和51)年。しかし、開発をはじめたのはその2年前からです。それまで麺つゆという商品は、おもに醤油メーカーが作っていました。6倍から8倍に薄めるタイプで、これらは実際に薄めると、塩分は麺つゆとして相応のものになっても、だしの風味が全く感じられず、とても蕎麦屋さんの麺つゆにはおよばない味でした。
「もっとおいしいつゆで蕎麦を食べたい」
「本格的な麺つゆができないだろうか」

素朴な思いつきですが、これが桃屋がつゆを開発したきっかけになったのです。しかし、老舗の蕎麦屋さんだって長年培ってきた秘伝の味ですから、そう簡単に本格的なおいしさにたどりつくことはできません。それで行ったのが、社長と開発課による蕎麦屋さん食べ歩き作戦です。
都内の有名な店、評判のよい店をしらみつぶしに、毎日食べ歩くのです。1軒の店でひとり3枚の蕎麦をとり、2杯分のつゆで3枚の蕎麦を食べると、1杯分のつゆは持ち帰りをお願いする。これを毎日続け、なんと2年間。この間、鰹節の選定やだしの取り方も研究を重ね、老舗の蕎麦屋さんと同じ方法を桃屋の工場でも採用し、その量産化にも成功致しました。こうして、ようやく納得のいく本格的な味、「つゆ」を世に出すことができたのです。ちなみに、関東には「やぶ」「更科」「砂場」と大きく分けると三つの系統の蕎麦屋さんがありますが、ヒントになったのは「やぶ」系のさっぱり味でした。

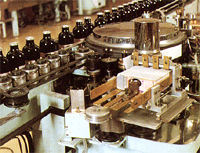

1980年当時の製造ライン
1976(昭和51)年にデビューし、あっという間にスターになったのがピンクレディ。その同じ年に、発売されたのが桃屋の「つゆ」です。当時の桃屋は、調味料分野への進出がテーマで、「焼肉のたれ」(昭和49年)、「キムチの素」(昭和50年)に続く、“第三の商品”として開発を始めました。しかし、発売の2年前に開発に着手した頃は、現在のようにポピュラーな商品となる事は予想だにしませんでした。いわゆる「こだわりの商品として「とりあえず出してみよう」「食べておいしいとわかってくださるお客様だけに買っていただければいい」と、スマッシュヒット狙いで発売した商品だったのです。
ところが、いざ発売してみると夏の間だけで12万ケースが売れるという大ヒット商品となりました。当社が「つゆ」を発売するまでの市販の「つゆのもと」は、醤油を主体とした商品設計だったのに対し、当社の「つゆ」は鰹だしを主体としたもの。こういった商品設計がお客様に支持された結果でした。翌年の昭和52年には前年の約10倍の爆発的な売れ行きを上げました。まさにピンクレディが「渚のシンドバッド」「UFO」など軒並み100万枚のレコードセールスをあげる中、「つゆ」も100万ケースを突破するビッグヒットを続けていったのです。
一方、桃屋の工場ではパニックさながらの忙しさで、朝6時から夜10時まで働いて、休みも取れませんでした。ひっぱりだことなった「つゆ」を欲しがる営業マンに工場長は「つゆが欲しければつくりに来い!」と訴え、開発課、研究所、事務系社員も交代で工場に行って働き、営業マンは土日にも工場へ出勤しました。まさに全社一丸となって、ビッグスター「つゆ」を支えたのです。

「つゆ」以前に販売されていた麺つゆは、おもに醤油メーカーがつくっており、濃縮率は6倍とか8倍というものがほとんどでした。しかし、薄めてみると塩分はちょうどよくても、だしの旨みは感じられません。そこで桃屋は希釈しても天然だしの旨みを充分引き出す濃縮「2倍」にしました。現在では2倍や3倍の濃縮率が主流ですが、当時は画期的なことでした。
また、つゆの容器に黒いガラスボトルを使ったのも初めての試み。黒ボトルは紫外線をほとんど通さないため、品質保持能力が高いのが特徴です。発売当時、食品に使う黒ボトルといえば高級ウイスキーぐらいしかありませんでした。桃屋から注文を受けた容器メーカーも驚いたそうです。そのうえ形は食卓においてもサマになるようにと、お蕎麦屋さんの徳利がモデル。そうめんなど、食べているうちにつゆが薄くなってしまうので、途中でつゆを足しますね。そんなとき「やぼな瓶を食卓に乗せるのは嫌」というのが桃屋のこだわり。中身から外見まですべてにこだわったのが「つゆ」なのです。


「桃屋のつゆ」は発売当初から黒ボトル。これは、透明ボトルに比べて紫外線を通す率が非常に低く、外光の影響を受けずにおいしさを守ってくれます。そして、桃屋が使う黒ボトルは、再生ガラス(カレット)※を90%以上使用したエコロジーボトルです。
また、液だれがおきにくいよう、壜の口の形をひと工夫しています。
※ 回収されたガラス壜を細かく砕き、キャップなどの異物を取り除いたもの。